教室の沿革
九州大学眼科開講120周年記念式典
2023年11月18日にホテル日航にて九州大学眼科開講120周年記念式典が開催されました。

眼科学教室の沿革

錦絵に描かれた東中洲の福岡医学校付属病院(明治20年)。中央に「病院」と見える。
九州大学医学部の起源は、1877年(明治10年)博多中之島元精錬所跡に福岡病院が新築されたことに始まり、1888年に県立福岡病院となった。1896年、県立福岡病院が福岡県中川郡千代村大字堅粕東松原(現在地)に移転した。1903年(明治36年)県立福岡病院は京都帝国大学福岡医科大学となり、1911年(明治44年)九州帝国大学医科大学となった。さらに、1919年に九州帝国大学医学部、戦後1947年(昭和22年)九州大学医学部と改称された。
九大眼科学講座は1903年に解剖学、内科学、外科学とともに医学部設立当初から設置され、小岩井長四郎が主長代理であったが、1905年ドイツチュービンゲン大学出身の大西克知が初代教授に就任した。
1926年(大正15年)岡山大教授であった庄司義治が二代目教授に就任、1940年(昭和15年)北海道大助教授であった田村茂美が三代目教授に就任した。
1959年(昭和34年)久留米大教授であった生井浩が四代目教授に就任した。1976年、鹿児島大教授であった谷口慶晃が五代目教授に就任、1983年、当時助教授であった猪俣孟が六代目教授に就任した。2001年に当時助教授であった石橋達朗が第七代目教授に就任し、2015年に当時山口大学教授であった園田康平が第八代目教授に就任し、現在に至っている。

錦絵に描かれた東中洲の福岡医学校付属病院(明治20年)。中央に「病院」と見える。
1877年~
| 1877年(明治10年) | 博多中之島元精錬所跡に福岡病院が新築される。 |
|---|---|
| 1888年 | 県立福岡病院となる。 |
| 1896年 | 県立福岡病院が福岡県中川郡千代村大字堅粕東松原(現在地)に移転。 |
1900年代
| 1903年(明治36年) | 県立福岡病院は京都帝国大学福岡医科大学となる。 |
|---|---|
| 1903年 | 解剖学、内科学、外科学とともに医学部設立当初から設置され、小岩井長四郎が主長代理となる。 |
| 1905年 | ドイツチュービンゲン大学出身の大西克知が初代教授に就任した。 |
| 1911年(明治44年) | 九州帝国大学医科大学となる。 |
| 1919年 | 九州帝国大学医学部となる。 |
| 1923年 | 大西教授の設計による旧眼科教室診療研究棟が完成。 |
| 1926年(大正15年) | 岡山大教授であった庄司義治が二代目教授に就任。 |
| 1940年(昭和15年) | 北海道大助教授であった田村茂美が三代目教授に就任。 |
| 1947年(昭和22年) | 九州大学医学部と改称された。 |
| 1959年(昭和34年) | 久留米大教授であった生井浩が四代目教授に就任。 |
| 1976年 | 鹿児島大教授であった谷口慶晃が五代目教授に就任。 |
| 1983年 | 当時助教授であった猪俣孟が六代目教授に就任。 |
2000年代
| 2001年 | 当時助教授であった石橋達朗が第七代目教授に就任。 |
|---|---|
| 2006年 | 附属病院新病棟完成に伴い眼科病棟は南棟11階に移転。 |
| 2009年 | 総合外来棟の完成に伴い眼科診療棟は2階に移転。 |
| 2015年 | 臨床研究棟を改築。山口大教授であった園田康平が第八代目教授に就任。 |
歴代教授と研究の動向
-

初代教授 大西克知
(おおにし・よしあきら)
大西教授の大いなる功績は日本眼科学会の創設と『日本眼科学会雑誌』の発刊であった。
教授は明治26(1893)年、旧制第三高等学校医学部(現在の岡山大学医学部)教授時代にわが国初の眼科専門誌『眼科雑誌』を創刊。その後、明治29(1896)年に須田卓爾、川上元次郎と協力して日本眼科学会を創設し、翌30(1897)年に『眼科雑誌』を廃刊して『日本眼科学会雑誌』の第1巻を発刊した。編集校正を同教授がほとんど独力で行い、第29巻(大正14年)まで九大眼科学教室において会誌を発行。明治41(1908)年には第12回日本眼科学会総会を主宰した。研究面では種々の眼科臨床的研究、トラコーマ病原に関する研究、眼球、顔筋、眼窩および頭蓋の解剖学的研究などを行なったが、特に臨床面において脈なし病は高安・大西病として有名である。ほかにも検査機器である『新刊萬国式視力表』の発行、手術用点眼瓶の改良、『プラス7Dの大西式柄付検眼鏡』の考案などの実績がある。
大正12(1923)年に竣工した総坪数2800坪、建坪1200坪の九大眼科教室と病棟は大西教授が自ら設計したもので、当時日本で最大規模のもの。ここで多くの人材を輩出し、以後の九大眼科の発展を支える基盤となった。
-

第2代教授 庄司義治
(しょうじ・よしはる)
庄司教授は大正10(1921)年から大正13(1924)年にかけ、文部省在外研究員としてフランスのソルボンヌ大学をはじめドイツ、イギリスに留学。眼屈折体の紫外線吸収に関する研究を行い、白内障や網膜剥離などの手術手技を学んだ。フランスとの親交により、昭和8(1933)年6月にはフランス政府からレジオン・ドヌール勲章を授与されている。
また、眼に関する生化学的研究や白内障などの眼科手術映画の製作を精力的に行なった。その手術撮影のために天井懸垂式のフィルム撮影機、同軸視野装置、腹部拡大装置、ピント装置などを次々に考案したという。
一方で地域住民のための無料開眼施療を実施。自ら地方の町村に出向いたほか、満州国や欧州諸国との交流に積極的に取り組んだ。昭和10(1935)年に長崎で開催された第39回日本眼科学会総会では「白内障の診断ならびに療法」と題し、特別講演を行なった。
-

第3代教授 田村茂美
(たむら・しげみ)
田村教授は第2次世界大戦の激化に伴って教室員が次々に応召され、人員が手薄になり、しかも物資が乏しいなかで残っている教室員をまとめて教育、診療、研究を指導した。
研究面では眼結核に関する研究や眼疾患の病理学、また戦時下医学の一端として、昼間および夜間視力の増強に関する研究を行なった。戦後は帰国した眼科医たちを積極的に迎え入れ、原子爆弾による眼障害に関する研究や、当時としてはまだめずらしかった角膜移植、コンタクトレンズに関する研究、中枢神経系と眼との関連などについて研究を進めた。戦時中の昭和18(1943)年には第16回九州眼科集談会を、戦後間もない昭和22(1947)年には第17回九州眼科集談会を主宰。昭和26(1951)年、第21回九州眼科集談会では「接着眼鏡の応用について」と題した講演を行い、教授自身が考案したポリメチルメタクリレート製のコンタクトレンズを披露した。さらに昭和27(1952)年4月に第56回日本眼科学会総会を主宰。昭和30(1955)年には九大眼科学教室開講50周年記念となる第101回九大眼科研究会を主宰し、同年、第59回日本眼科学会総会では「中枢神経系と眼」と題する特別講演を行なっている。

-

第4代教授 生井浩
(いくい・ひろし)
生井教授は昭和31(1956)年から翌年にかけてハーバード大学に留学し、眼病理学を研究。帰国後、昭和34(1959)年に教授に就任してまもなく、他の大学に先駆けて電子顕微鏡を導入した。
電子顕微鏡は眼病理学の研究推進に大いに寄与し、九州大学眼病理研究の発展の礎となる。その後、交感性眼炎およびフォークト・小柳・原田病、ベーチェット病、高血圧網膜症、動脈硬化性網膜症、腎性網膜症、中心性網脈絡膜症、緑内障、脈絡膜悪性黒色種、網膜芽細胞腫、眼微小循環などの研究を経て昭和49(1974)年、第78回日本眼科学会総会で「グリア細胞系を中心とした網膜の病理」と題した特別講演を行なった。世界に誇る眼病理学者として、発表した学術論文は330、著書は30以上にのぼるなど、数多くの輝かしい業績を残している。また教育にも力を入れていた生井教授は昭和38(1963)年、教務委員長として医学生のベッドサイド教育を導入。この試みは全国に広がり、今でも医学教育の要となっている。
昭和43(1968)年、九州大学付属看護学校の校長に就任。当時は指導教官の数もわずかであったが、医療現場は医師だけでなくさまざまなスタッフの力によって支えられているのだと、看護教育の重要性を説いた。看護学生が勉学に励めるよう環境改善にも力を注ぎ、昭和46(1970)年には看護学生寮の改築を行なっている。
-

第5代教授 谷口慶晃
(たにぐち・よしあき)
谷口教授は臨床研究を推進するため、緑内障や未熟児網膜症、フォークト・小柳・原田病、ベーチェット病、眼腫瘍、糖尿病網膜症などの特殊疾患を診断・治療する特殊再来の制度を設置。これにより診療が専門化し臨床レベルが向上したが、その伝統は現在の特殊再来にも色濃く受け継がれている。
教授は糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症の研究に努めたほか、海外から多くの留学生も受け入れ、新研究棟における研究を推進。電子顕微鏡による眼組織病理学の草分けとして活躍し、当時の糖尿病網膜症やその合併症の第一人者として広く知られた。
昭和36(1961)年に東京で開催された第65回日本眼科学会総会では、助教授として宿題報告「葡萄膜を中心とした眼組織の電子顕微鏡による研究」を担当。昭和57(1982)年の第36回日本臨床眼科学会では「網膜循環障害の病態」を教育講演、昭和55(1980)年には第84回日本眼科学会総会を主宰している。また教室から大島健司(元福岡大学教授)、大野新治(元佐賀大学教授)らを大学教授に輩出した。
-

第6代教授 猪俣孟
(いのまた・はじめ)
猪俣教授は昭和42(1967)年にニューヨーク、コロンビア大学に留学し、G.K. Smelser教授のもとで房水流出路を研究。昭和58(1983)年に第6代教授に就任してからは緑内障、ぶどう膜炎、眼内レンズ、糖尿病網膜症、網膜血管閉塞症、眼腫瘍などの病理学的研究を進め、「眼病理の九大」という確固たる流れを世界に知らしめた。
平成3(1991)年、「日米共同国際学術研究」という名目で南カリフォルニア大学と「ぶどう膜炎の臨床と病理」について共同研究。平成5(1993)年には第47回日本臨床眼科学会で「落屑緑内障の臨床と病理」と題して特別講演を行なった。
このころから教室全体のテーマとして「眼血管新生」を掲げて研究を進め、平成7(1995)年、第99回日本眼科学会総会で「血管新生の機序とその抑制」と題して教育講演を、平成9(1997)年、第101回日本眼科学会総会で「眼内血管新生」と題して特別講演を実施。平成10(1998)年には第102回日本眼科学会総会を主宰した。
一方、院内では従来の外来新患の予約制を廃止した自由な診療を導入。病棟には6か月を任期とする主任病棟医をおき、任期終了時に卒業試験と称して臨床成果を報告させ、臨床力の向上を図るなど、平成13(2001)年3月に定年で退官するまでのあいだ教室の体制に大きな変化をもたらした。また教室から向野和雄(元北里大学教授)、宇賀茂三(元北里大学教授)、大西克尚(元和歌山県立大学教授)、田原昭彦(元産業医科大学教授)らを大学教授に輩出した。
-
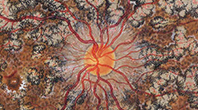
第7代教授 石橋達朗
(いしばし・たつろう)
石橋教授は九大眼科の伝統である眼病理学を継承発展させた。眼血管新生を教室のテーマとして継続推進し、加齢黄斑変性・糖尿病網膜症に関して臨床と基礎の両面から研究。トリアムシノロンやBBGといった手術補助剤が九大から世界に実用化され、手術件数が伸び、若手サージャンが数多く育成された。
研究室では分子生物学や遺伝子操作などの新しい手法を取り入れることで教室員のモチベーションを向上させ、大学院進学者・海外留学者が増加。平成11(1999)年、第103回日本眼科学会総会では宿題報告「眼内循環 眼内血管病変の細胞生物学」を担当。基礎から臨床、さらには将来の遺伝子治療までを網羅し、今後の眼科学の方向性を指し示した。また平成15(2003)年に第42回日本網膜硝子体学会を、平成21(2009)年には第63回日本臨床眼科学会総会を主宰。平成23(2011)年の第115回日本眼科学会総会では特別講演「網膜の包括的神経保護〜臨床応用への挑戦〜」を担当。平成23(2011)年6月、第25代日本眼科学会理事長に就任し、平成26年(2014)第34回国際眼科学会(WOC)を主催した。平成25(2013)年に九州大学副学長、平成26(2014)年より九州大学病院長に就任。その後平成30(2018)年より九州大学理事、令和2(2020)年10月より九州大学総長となり現在に至る。教室から坂本泰二(鹿児島大学教授)、吉冨健志(秋田大学教授)、村田敏規(信州大学教授)、内尾英一(福岡大学教授)、向野利寛(福岡大学筑紫病院教授)、久保田敏昭(大分大学教授)、園田康平(山口大学教授、第8代九州大学教授)、川野庸一(福岡歯科大学教授)、江内田寛(佐賀大学教授)らを大学教授に輩出した。









